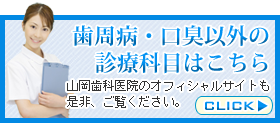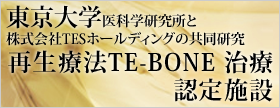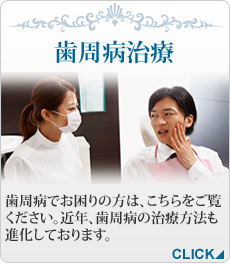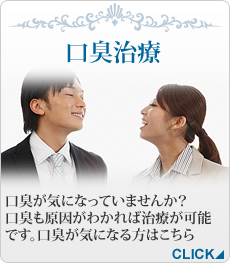歯周病が進行して細菌が増殖すると、歯肉の血管から菌が侵入して増殖し、血液に乗って全身にさまざまな悪影響を及ぼします。
歯周病が進行して細菌が増殖すると、歯肉の血管から菌が侵入して増殖し、血液に乗って全身にさまざまな悪影響を及ぼします。
最近の研究によれば糖尿病や心臓血管病などが歯周病に関連する疾患とされており、肺炎や骨粗しょう症、腎炎、関節炎、発熱などへの関連も疑われています。さらに妊婦が歯周病にかかっている場合、低体重児出産や早産を起こす危険性が高くなるという研究結果もあります。
歯周病治療は、羽曳野市の歯科医院・歯医者 山岡歯科医院へ
 歯周病は腎障害、網膜症、神経障害、大血管障害、末梢血管障害に次ぐ糖尿病の第6の慢性合併症とも言われています。
歯周病は腎障害、網膜症、神経障害、大血管障害、末梢血管障害に次ぐ糖尿病の第6の慢性合併症とも言われています。
近年その深い関連性はさまざまな研究から明らかにされてきており、右記の図にあるようなリスク要因から歯周病を発症、そして増悪させるといわれています。
特に肥満を伴う糖尿病患者では、TNF-αという物質が脂肪細胞から多量に産生されますが、これは受容体を介して糖の取り込みを阻害しインスリン抵抗性に関与しているといわれています。
TNF-αは、歯周病原細菌の細胞壁に存在するLPS(リポ多糖)により誘引され、炎症巣からも産生されるため、さらにTNF-αが増加し、よりインスリン抵抗性が悪化するなど歯槽骨吸収との深い関わりが注目されています。そのため、近年では糖尿病患者だけでなく、肥満も歯周病に関連しているといわれ、歯周病もまた内臓脂肪症候群(メタボリック シンドローム)の1つの指標であると言えるでしょう。
歯周炎局所に抗生物質を用いて歯周病原細菌を抑制すると血中TNF-α濃度が有意に低下し、それに伴いインスリン抵抗性が改善するとともに、HbA1c 値(高血糖状態が長く続くと増えるので長期的な血糖管理の指標に用いられる)も低下することが報告されています。
すなわち糖尿病や肥満は、歯周病のリスク要因であるとともに、歯周病を放置すれば糖尿病の病状が悪化する可能性があるということになります。言い換えれば、歯周病の治療をすることにより糖尿病のインスリン抵抗性を改善するということになり、糖尿病に苦しむ患者には大きなモチベーションとなるでしょう。タバコの煙には数千種類の化学物質が含まれていて、健康を害する可能性が高く、心臓疾患やガンなどの命を奪う病気と関連が高いあることは多くのメディアでも取り上げられています。
しかし、歯周病とも深い関連があることは、日本ではまだあまり知られておりません。
予防先進国の欧米各国ではすでに20年以上前から喫煙者の歯周病は、吸わない人と比べて重度であると研究されております。1日10本以上喫煙すると歯周病にかかる危険は5.4倍あり、歯周病を悪化、進行させ、治療の予後にも悪影響を及ぼし歯周病の再発や歯の喪失にも関与します。
したがって、歯周病の治療を受けたあと良い状態を保つには、禁煙が大変重要になります。禁煙することで、歯周病のリスクは4割もへります。もし、どうしてもタバコがやめられない人は、せめてタバコの本数を減らし、これまで以上に歯磨きをするようにしてください。
タバコの煙に含まれる一酸化炭素は組織への酸素供給を妨げ、ニコチンは一種の神経毒で、血管収縮作用によって歯肉内の血流量が低下することで酸欠・栄養不足状態になります。また、ニコチンは体を守る免疫機能も狂わせるため、病気に対する抵抗力が落ちたりアレルギーが出やすくなったりします。
すると、傷を治そうとする再生能力が低下してしまい手術後も治りにくくなったり、歯周病菌の感染を防げなくなったりします。